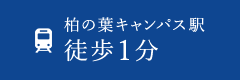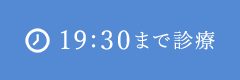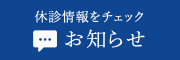高血圧と食事の関連性
高血圧は、遺伝や肥満、運動不足、飲酒、ストレスなど様々な要因が絡み合って起こりますが、中でも日々の食事は血圧に直接影響を与えます。特に、塩分の摂りすぎや過食、偏った食生活は血圧上昇のリスクを高めます。ここでは、高血圧を改善・予防するために、どのような食生活を心がけるべきか、そのポイントをご紹介します。
血圧が高い方が摂取を
控えるべきもの
高血圧と診断された方が特に気をつけたいのが、以下の2点です。
①塩分が高いもの

日本高血圧学会が推奨する1日の塩分摂取目標は6g未満です。しかし、厚生労働省の国民健康・栄養調査によると、日本人の平均摂取量はこれを大きく上回っています(男性約10.8g、女性約9.2g)。このことから、多くの方にとって減塩が重要な課題であることが分かります。
塩分の摂取量を減らすためには、以下のような工夫が有効です。
- 薄味に慣れる: 料理の味付けを徐々に薄くしていく
- 調味料を工夫する: 醤油やソースはかけすぎず、減塩タイプを活用する
- 出汁や香辛料を活用する: 旨味や風味で満足感を高める
- 加工食品を減らす: 漬物や練り物、インスタント食品などは塩分が多い傾向があります
また、日本高血圧学会減塩・栄養委員会では、減塩率20%以上の食品リスト(「JSH減塩食品リスト」)を公開しています。醤油、だし、ドレッシング、漬物、加工品、インスタント麺など、具体的な商品名で紹介されているので、ぜひ参考にしてみてください。
出典:日本高血圧学会 減塩・栄養委員会
なぜ塩分を摂りすぎると血圧が上がるのか?
体内の塩分濃度は常に一定に保たれています。塩分を過剰に摂取すると、体はその濃度を下げようとして水分を溜め込みます。その結果、血液量が増え、心臓から送り出される血液の勢いが強まり、血管にかかる圧力(血圧)が上昇するのです。高血圧の方の腎臓では、塩分の摂取に伴い血管が収縮しやすくなることも、血圧上昇の一因となります。
②アルコール
 習慣的なアルコールの過剰摂取は、血圧上昇の原因となることが報告されています。アルコール量を減らすことで、血圧が低下するケースも少なくありません。
習慣的なアルコールの過剰摂取は、血圧上昇の原因となることが報告されています。アルコール量を減らすことで、血圧が低下するケースも少なくありません。
高血圧の予防や改善のためには、適切な飲酒量を守ることが大切です。厚生労働省e-ヘルスネットによると、目安として男性は日本酒1合程度(ビール中瓶1本、焼酎0.6合、ウイスキーダブル1杯、ワイン1/4本、缶チューハイロング缶1本程度)が望ましいとされています。女性はその約半分が目安です。
出典:厚生労働省 e-ヘルスネット
なぜアルコールを摂りすぎると血圧が上がるのか?
アルコール摂取量が増えると、アルコールに含まれる糖質や、おつまみとして選ばれがちな塩分・脂質の多いメニューによって、栄養バランスが偏りやすくなります。また、アルコールは肝臓だけでなく血管にも負担をかけ、心臓病や脳卒中のリスクを高める可能性があります。飲酒は適量を心がけ、休肝日を設けるなど工夫しましょう。
高血圧改善のための
食事のポイント
高血圧の食事療法では、減塩、適切なアルコール摂取量に加え、カリウムの積極的な摂取が重要です。
- 出汁や薬味を上手に使う: 減塩食は味が薄く感じがちですが、鰹節や昆布の出汁、生姜、ネギ、大葉などの薬味を上手に使うことで、風味豊かで満足感のある食事になります。
- 和食を取り入れる: 魚はDHAやEPAといった良質な脂質を含み、野菜や海藻類には血管の健康に役立つ水溶性食物繊維が豊富です。これらを多く取り入れやすい和食は、高血圧改善に適した食生活と言えます。
- カリウムを積極的に摂る: カリウムは体内の余分なナトリウム(塩分)を体外へ排出するのを助ける働きがあります。ほうれん草、かぼちゃ、キノコ類、海藻類、果物などに多く含まれます。果物の果糖が気になる場合は、野菜から摂ることを意識しましょう。
食事以外の生活習慣も大切に
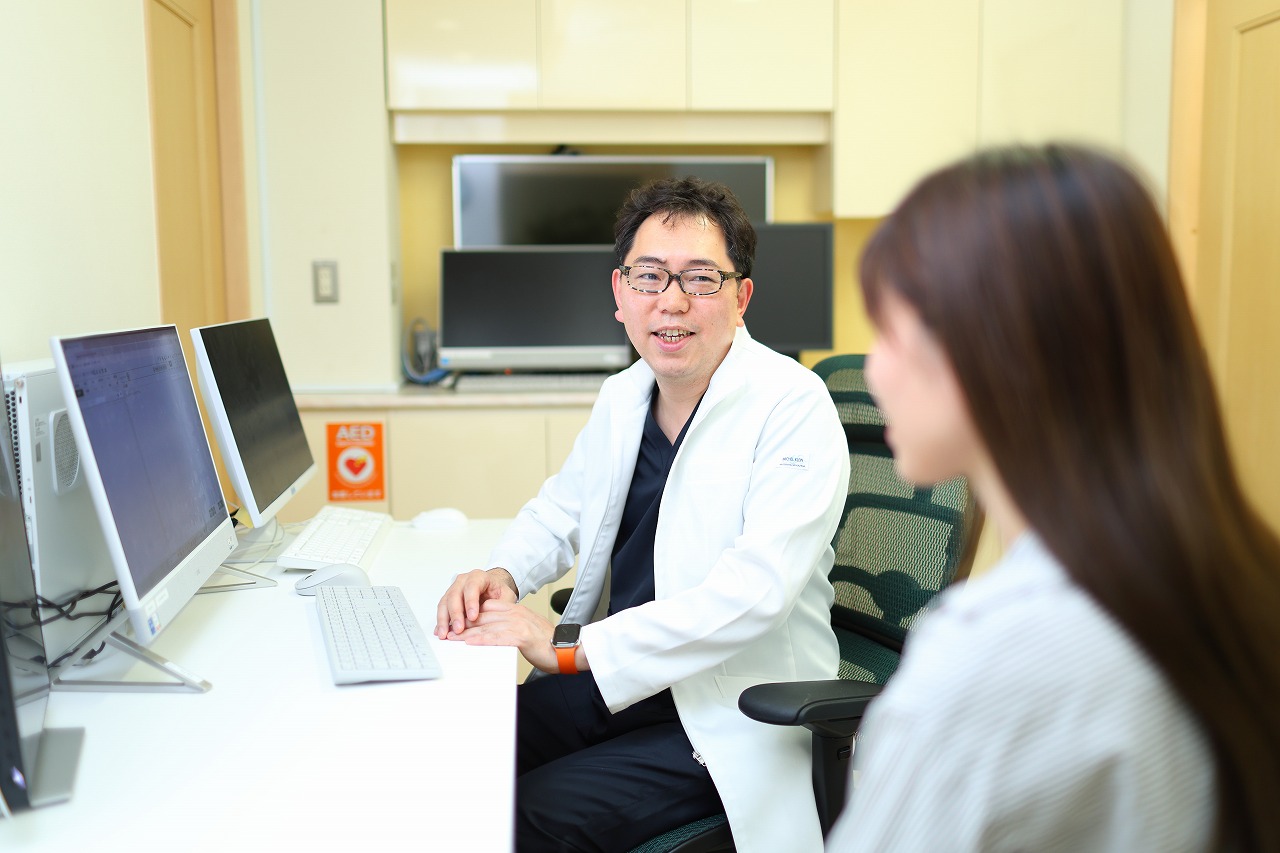 高血圧が気になる場合、まずは食事内容の見直しが第一歩です。今回ご紹介した塩分やアルコール量のコントロール、そして野菜や果物の摂取を意識してみましょう。
高血圧が気になる場合、まずは食事内容の見直しが第一歩です。今回ご紹介した塩分やアルコール量のコントロール、そして野菜や果物の摂取を意識してみましょう。
しかし、高血圧の改善は食事だけでなく、喫煙、運動不足、ストレス過多などもリスク要因となるため、これらを正しく認識し、日々の生活習慣全体を見直すことが重要です。
高血圧は自覚症状が少ないため、治療の必要性を感じにくい、あるいは生活習慣の改善を継続するのが難しいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、本格的な投薬治療が始まる前や、他の病気が併発する前にご自身の状態を自覚し、早めに対策を始めることが肝心です。
ララクリニック柏の葉では、管理栄養士による食事指導も行っております。お気軽にご相談ください。